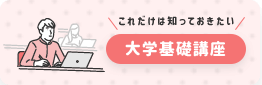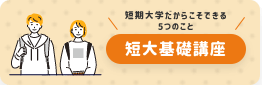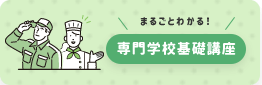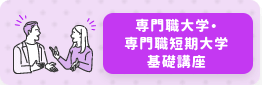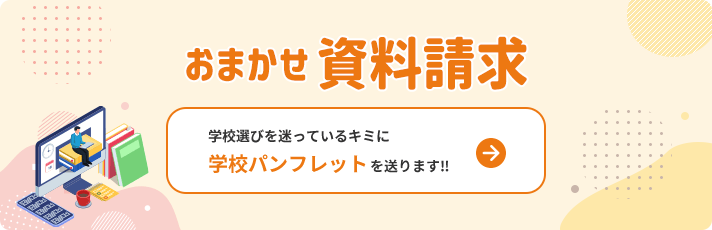専門学校とはどんな学校?
専門学校ってどのような学校なの?
専門学校とは、入学資格が高卒以上の専修学校専門課程のことで、各都道府県知事等の認可を受けて設置されている学校のことを指します。その名の通り、専門学校では、医療や美容、福祉、保育、情報処理、デザイン、ゲームなど各分野に関した専門性の高い知識・技術を教えており、それぞれの業界の最前線で活躍できる即戦力を育成しています。
専門学校で学べる分野はこちら
専門学校は認可を受けている高等教育機関の一つですが、他に高等課程を持つ高等専修学校や一般課程をもつ専修学校などがあります。これらを総じて「専修学校」と呼びます。ただし、「専修学校=専門学校」というわけではありません。専修学校の中で専門課程のある学校のことだけを「専門学校」と称します。

大学や短大、専門職大学との違いは?
専門学校と大学・短期大学の違いは何でしょうか?大学・短大の教育目的は広く教養を高めること、専門的な学問や学術の研究を行うことです。一部の学部・学科を除いて、専門の職業に就くための教育は行っていません。そのような中、2019年度に専門職大学・専門職短期大学が開設されました。職業教育に特化しつつ、理論も多く学び、学問の研究も行っています。
一方、専門学校は職業に直結した技能教育が中心です。資格を取得することで活かせる職業も明確化し、的をしぼった就職活動が可能になります。就職後に即戦力として働ける可能性は高まりますが、学んだ分野に関連しない職業に就くのは難しくなります。専門学校へ進学する場合は、将来就きたい職業を明確にしておくことが最も重要なこととなります。
| 専門学校 | 大学・短期大学 | 専門職大学 専門職短期大学 |
|
|---|---|---|---|
| 教育目的 | 仕事や生活に必要な資格・技術を身につける |
|
実践的な職業教育を行い、 専門的な研究をし、教養を深める |
| 年限 | 1~4年 |
|
|
| 授業内容 | 実践を重視した実習・演習が中心 | 理論を重視した座学・演習・実験が中心 | 理論と実践をともに重視した 座学・演習・実習 |
| 卒業条件(単位) | 年間:800時間以上(単位制は大学・短大に準ずる) |
|
|
| 教員 | 実務に関する知識・技能を有する 実務家教員 | 研究実績や特殊技能を有する 研究者職員 | 実務家教員(専任教員の4割以上)+研究者職員 |
| 学位・称号 |
|
|
|
※学校教育法の一部改正を受け、2026年度から専門学校の履修制度が段階的に単位制に移行していく見込みです。
専門学校とその他の教育機関との違いは?
専修学校と同様に職業教育を行う教育機関として、「各種学校」という学校もあります。各種学校も専修学校と同じく、各都道府県知事より認可を受けている学校となります。
その他、専修学校とは入学資格などの認可基準が大きく異なっているものとして無認可校があります。専門学校や各種学校などとは異なり、都道府県知事などの認可を受けていない教育機関になります。専門学校は細かな基準・原則のもと認可を受けています(認可を受けていないと「専門学校」と名乗ることはできません)が、無認可校は基準・原則がないため修業期間やカリキュラムなど自由度が高いのが特徴です。ただ注意すべき点として、無認可であるため受けられない奨学金制度や割引などがあります。また、万一倒産してしまったりした際に認可校のような公的な救済措置がありません。気になる学校がある場合は、専門学校なのか、無認可校なのか、しっかり調べておきましょう。
| 認可校 | 無認可校 | ||
|---|---|---|---|
| 専修学校 | 各種学校 | ||
| 入学対象者 |
|
|
|
| 修業年限 | 1年以上 | 1年以上(ただし、3か月、6か月のものもある) | 規定なし(短期間のもの、週当たり時間数の少ないものも多い) |
| 年間授業時間数 | 800時間以上(夜間は450時間以上)(※) | 680時間以上(1年未満の場合は比例して減る) |
|
| 国の教育ローン | 利用可能(条件あり) | 原則として利用できないが、一部利用可能(条件あり) | |
| 日本学生支援機構奨学金 | 利用可能(条件あり) | 原則として利用できない | |
| 交通費 | 通学定期が利用できる | 通学定期が利用できる(条件あり) | 原則として学割は適用されない |
| 学費 | 原則として在籍した年数分だけかかる | 半年以下の短期間のものであれば、認可校に比べ安い場合がある | |
| 卒業後の学歴 | 専修学校卒 | 各種学校卒 | 正式な学歴とは認められない |
※学校教育法の一部改正を受け、2026年度から専門学校の履修制度が段階的に単位制に移行していく見込みです。
職業に直結した技能教育が魅力!
専門学校の一番の魅力は職業に直結した技能教育といえます。専門学校では、専門的な知識や技術を習得するために、理論の学習以上に「実際に行い、身体で覚える」という実践的な授業が重視されています。実習中心のカリキュラムなので、就職後即戦力として活躍できるスキルを磨くことができます。
また、それぞれの分野に特化したことを学べるので、希望する職業に必要な資格の取得、そしてスキルや知識を生かせる企業への就職が期待できます。施設・設備に力を入れている学校も多く、将来働く職場(店舗や工場など)と同じ環境が用意されていることもあります。また、講師の多くは現場で活躍するプロフェッショナルであり、なかには業界の著名人を招いての授業を行う場合もあります。
国が認定!実践的職業教育を実施。「職業実践専門課程」制度
文部科学省は、企業等と密接に連携し、より実践的な職業教育に取り組む専門学校の〝学科〟を「職業実践専門課程」として認定しています(総授業時間数1,700時間以上などの認定要件あり)。「職業に必要な最新の実務の知識・技術・技能を育成する学科」として国が認定した学科として、学校のパンフレットやHP等にも記載されている場合もありますのでチェックしてみましょう《全国で1,110校3,199学科認定(平成25~令和5年度)》
「職業実践専門課程」認定要件
実践を重視した授業で即戦力へ
大学での学びは学問の追究や研究を中心に幅広い見識を身につけるのに対し、専門学校では職業に必要な能力の育成を目指しています。そのため、専門学校の授業の多くは実習を中心に構成されており、実習を通じて技術や知識を身につけることに重点を置いたカリキュラムとなっています。その分、一度でも休むと授業についていけなくなる可能性もあります。学ぶ目的や将来の目標を明確にして、遅刻や欠席をしないように心がけましょう。
専門学校・大学のカリキュラム比較(例)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 食品衛生学 | 集団調理 | 栄養学 | 調理基本・調理科学 | 基本調理実習 (中国) |
| 2 | 公衆衛生学 | 一般常識 | 食品衛生学 | 公衆衛生学 | |
| 3 | 基本調理実習 (西洋) |
食品衛生学 | 基本調理実習 (日本) |
食品学 | 食品衛生実習 |
| 4 | 食文化概論 | - | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランス語 | 健康スポーツ(体育) | 実践調理学実習 | - | 英語 |
| 2 | - | - | - | 情報処理演習 | |
| 3 | キャリアデザイン | 調理学 | 健康の科学 | 基礎栄養学 | 基礎生化学 |
| 4 | - | 家政学概論 | 日本語表現法 | 現代国家と法 | - |
学校ごとに学べる内容も異なる!?
実習が学びの軸である専門学校ですが、授業の内容も確認が必要です。「希望する分野を学べる学校だからどこに行っても同じ」というわけではありません。例えば、同じ分野を学べる専門学校が2つあったとしても、卒業時に同じ資格が取得できているとは限らないのです。
専門学校の授業はバラエティに富んでおり、施設・設備や講師陣など、学校それぞれの強みを活かした授業が展開されています。そのため取得できる資格も異なる場合があるのです。
また実習についても、どのような場所で実習を行うのか、校外での実習はどれほどあるのか、学校によって異なります。行きたい分野の学科ではどのような授業が行われているのか、カリキュラムの内容を確認しましょう。
大学との併修や編入学も可能
専門学校で2年以上、総授業時間数が1,700時間以上の文部科学大臣が指定した学科を修了すると「専門士」の称号が与えられ、大学・専門職大学への編入学が可能になります。一定の要件を満たした4年以上の場合は「高度専門士」となり、大学院への入学が可能です。なかには大学・短期大学の通信教育を利用した併修コースを持つ学校もあり、専門学校卒業と大学(短期大学)卒業資格を得られます。
| 専門学校 | 大学・短期大学 | 専門職大学 専門職短期大学 |
|
|---|---|---|---|
| 編入学 | 大学・専門職大学・専門学校 (2年制以上の基準あり)間で可能 | 大学・短期大学間で可能 | 専門学校・短期大学以外に社会人の編入学生も受け入れあり |
| 単位互換 | 一部の学校で可能 | 大学・短期大学間で可能 | 入学前に実務経験や資格取得などで実績のある者へ単位が与えられる場合あり |
専門学校基礎講座【目次】
-
01
-
02
-
03
-
04
-
05
-
06
-
07
-
08
-
09