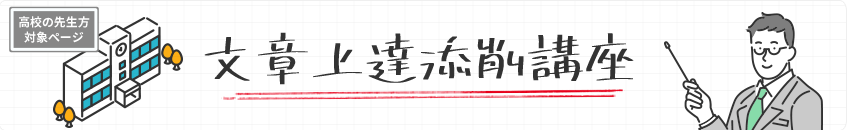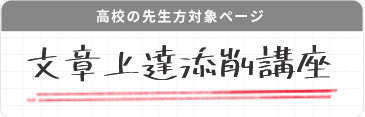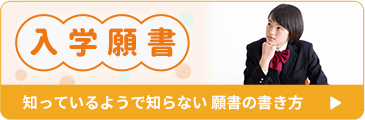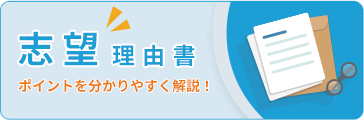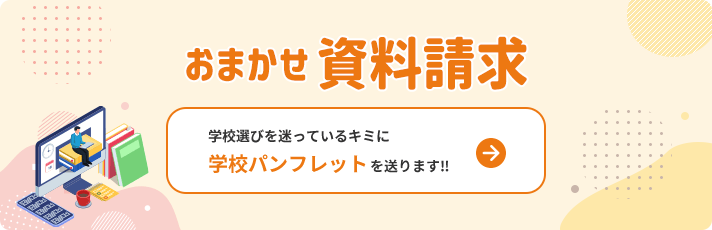STEP.4 小論文の設問要求を読み取ろう
1. 小論文の出題形式
小論文試験では設問文を通してテーマが与えられますが、設問によっては課題文やグラフなどと合わせて出題されます。しかし、いずれの場合も設問文や資料を通して与えられた要求に沿って答案を書かなくては、設問に解答したことになりません。設問文に基づき、何を答えるべきか考えることは、主張を論じるための第一歩です。
1テーマ型(設問文のみの提示)
設問文を読み、与えられたテーマに沿って主張を論じる形式です。出題されるテーマはさまざまですが、以下の形式で出題されることが多いです。
(1)論じるべきことが指示されている設問
- <例1> 賛成か反対か/是非/ A or B など、主張を選択させる設問
-
- 設問:
- 児童にとって学習塾は必要か。 ➡ 主張:必要である。/必要ではない。
- <例2> 対策/改善案/対処法など、課題解決を論じさせる設問
-
- 設問:
- 「歩きスマホ」を減らすための方法を述べよ。 ➡ 主張:取り締まる条例を定める
- <例3> 「影響」・「役割」・「意義」など、指定された事柄を論じさせる設問
-
- 設問:
- オリンピックを招致する意義は何か。 ➡ 主張:国際交流のあり方を考えることだ。
指示に沿うことは必須条件です。「意義」を問われているのに「賛成」や「反対」を述べるのは的外れな解答ということになります。むしろ、指示に沿って考えることでどのように論じるかも定めやすくなります。
(2)テーマについて、自由に論じさせる設問
- < 例 >
-
- 設問:
- 学校制服の着用についてあなたの考えを述べなさい。
- 主張:
- (問題提起:着用することの意義は何か?) ➡ 着用には~という意義がある。
(問題提起:着用を義務化するべきか否か?) ➡ 義務化に賛成である。/ 反対である。
(問題提起:着用に伴う課題はないか?) ➡ ~という課題がある。それには~で対処すべきだ。
このような設問には「~について述べよ」とあるのみで、何を答えればよいか指示がありません。この場合は、解き明かすべき問題を自ら設定して、それに対する答えを考える必要があります。
では、例題の「学校制服の着用について」という設問はどう考えればよいでしょうか。「制服」は衣服としてだけではなく、制度の「制」がつくように、規律や義務と密接なテーマです。ここから、「なぜ制服を着用しなくてはならないのか」という問いがしばしば議論の対象になります。
この問いを踏まえ、「制服を着用することの意義は何か」や「制服にどのような役割があるのか」などの問題設定は考察の余地がありそうです(➡指定された事柄を論じさせる設問)。他にも、制服の利点や欠点などを踏まえ、「着用を義務化するべきか」という問いへの答えを論じることもできます(➡主張を選択させる設問)。また、「着用に伴う課題はないか」を問い、その対策や改善案を答えるという問題も成り立つでしょう(➡課題解決を論じさせる設問)。
何よりも、テーマについて、自らの知識を基に疑問を投げかけ、論じたい問題を設定することが重要です。このように、答えにたどり着くために問題を設定していくことを問題提起と言います。自ら問題を設定し、正解のない課題に対処していく力は、進学後の学習や調査・研究をはじめ、今後の社会で広く求められます。小論文を通して訓練していきましょう。
2 課題文型(課題文の提示)
与えられた課題文を読み、その内容を踏まえて主張を論じる形式です。
まず、文章内で示されている要点を読み取り、設問全体のテーマをおさえます。そして、設問文に沿って要点やテーマに対するあなたの主張を考えましょう。国語の文章題のように、設問文を先に読み、問題の指示を理解したうえで文章を読むことで要点を見つけやすくなります。
- <例1>
-
- 設問1:
- 課題文Aを200字以内で要約しなさい。
- 設問2:
- 課題文Aについて、あなたの考えを600字以内で述べなさい。
- <例2>
-
- 設問:
- 課題文Aを読み、筆者が主張していることについてあなたの考えを述べなさい。
例1では要約問題と論述問題が分かれていますので、設問1をSTEP3の「要約の要領をつかもう」で学んだ要約の手順で記述します。
一方、例2では要約は求められていません。しかし、主張を論じる前提になりますので、序論で課題文の要点には触れましょう。
3 図表型(グラフ・図表・イラストなどの提示)
与えられたグラフや図表などの資料を読み、その内容を踏まえて主張を論じる形式です。
まず、資料に表れている顕著な差や傾向、また、資料が複数ある場合はそれらの関係性を探します。続いて、それらの資料の背景にある情報を読み取り、設問全体のテーマをおさえます。そして、設問文に沿って読み取った情報やテーマに対するあなたの主張を考えましょう。課題文型同様、先に設問文を読むことで資料に隠された情報を見つけやすくなります。
- <例1>
-
- 設問:
- 図A(「日本人の平均寿命の変遷」)と図B(「日本人の死因となる疾病の順位」)を読み、日本の医療の課題についてあなたの考えを述べなさい。
単に「日本の医療の課題」を論じるのではなく、図A・Bによって取り上げるべき「課題」を絞り込むことができます。資料に隠されている情報を理解できているほど、何を論じるかが定めやすくなります。
目次
-
STEP.1
-
STEP.2
-
STEP.3
-
STEP.4
-
STEP.5
-
STEP.6